食中毒にご注意ください!
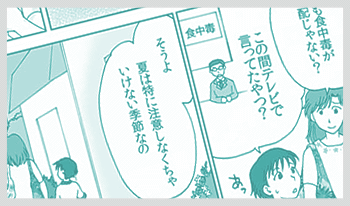 |
4月末に発生したO-111による集団食中毒事件で、食中毒への不安が高まっています。
O-111や毎年話題になるO-157とは、大腸菌のなかでも、激しい下痢や出血を伴う腸炎、溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こすおそれのある腸管 出血性大腸菌のこと。通常は、肉の食用部分にはないのですが、家畜の腸内、皮膚についているものが、解体の際に肉の表面に移ることがあるのです。毒素を出 し、細菌数が少なくても感染するのが特徴です。
予防のためには、肉は十分に加熱(中心部が75℃以上で1分以上)する、ひき肉、成形肉はとくによく火を通す、生肉にふれた野菜などは火を通してから食べるなどの注意が必要です。焼き肉や鍋では、生肉に触れる調理用の箸やトングと、食事用の箸を必ず分けましょう。
生肉を食べるのは、抵抗力の弱い子どもや高齢者などは避け、大人もリスクがあることを理解した上にしましょう。
気温の高くなる7月からは、ほかの食中毒にも注意の必要な時期です。主に魚介類を介して腸炎ビブリオ、鶏卵を介し最も発生数の多いサルモネラ菌など、さま ざまな細菌が食中毒の原因となります。また、飲食店での食中毒に注意がいきがちですが、家庭での発生も全体の20%と高く、家庭内での用心も大切です。
予防は手洗いから。調理前、食事の前はもちろん、調理中も肉や魚を触った後、鼻をかんだ後など、こまめにせっけんを使って洗いましょう。肉を調理したあとは、熱湯などで器具を消毒しましょう。
食品購入の際は、鮮度や消費期限をチェックします。購入後は、細菌が増えないように、すみやかに冷蔵庫で保存しましょう。例えば、O157は室温で10~15分で2倍に増えます。
残った食品は冷蔵庫などで保存し、再加熱してから食べるようにしましょう。少しでも不安があったら、口にしないことが大切です。